ベンチャー業界のプレイヤーの一つとして、CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)があります。一般的なVCとの違いや、ファンドの活動に影響はあるのでしょうか。今回は、CVCの組成を検討している方に、必要な情報について解説します。
2021.12.21(最終更新日:2024.02.01)

ベンチャー業界のプレイヤーの一つとして、CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)があります。一般的なVCとの違いや、ファンドの活動に影響はあるのでしょうか。今回は、CVCの組成を検討している方に、必要な情報について解説します。
2021.12.21(最終更新日:2024.02.01)
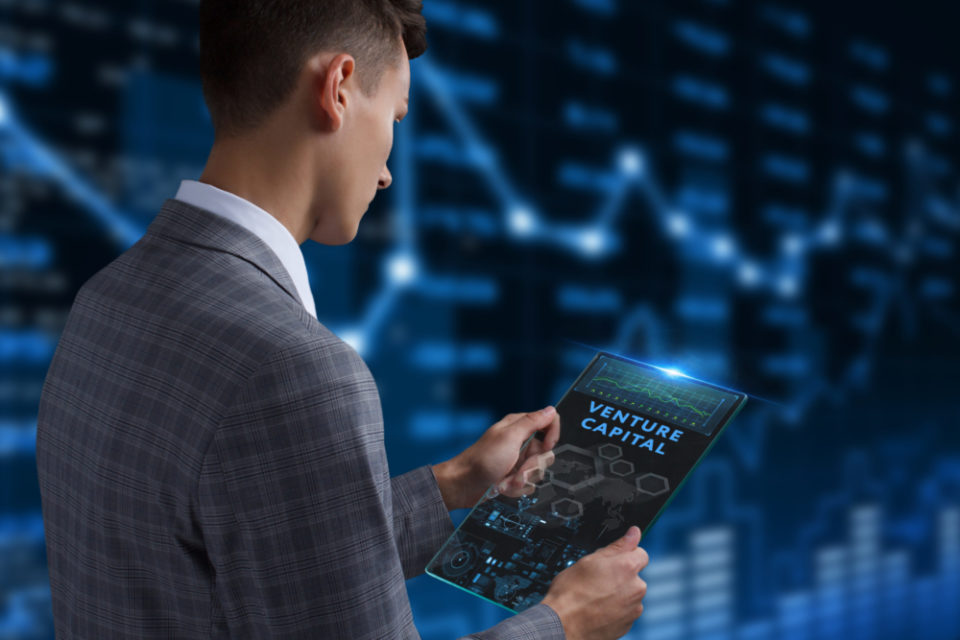
CVCはCorporate Venture Capitalの略で、事業会社がその傘下に持つVCとなります。
VCとは異なる目的で組成されますので、運用方法やマネジメント、投資先の管理方法、成果の測定方法なども一般的なVCとは異なります。
CVCはベンチャー企業に出資して運用しますが、その運用は自社のリソースで行うケースと外部のVC等に委託するケースがあります。
自社のリソースで行う場合、社内の投資部門や投資子会社を通したり、運用に精通した外部の専門家を招いたりします。
外部のVCに委託する場合は、専門的に活動しているプレーヤーに運用を委託することで、経験値不足やリソース不足の解決を図ります。

CVCと一般的なVCでは、その組成の目的に明確な違いがあります。 一般的なVCの活動は投資利益の追求を主軸とします。
CVCもファンドである以上、投資利益を全く追求しないわけにはいきません。ですが、主目的は会社本体の事業の成長や多角化にあります。その点がCVCの組成や運営の方法を、一般的なVCと大きく違うものにしている原因です。
事業会社がベンチャー投資をするにあたっては、直接投資することもありますし、間接的に投資するという方法もあります。
合弁のような形で、他社と共同でCVCを設立することもあります。独自にCVCを組成する場合には、まず投資会社を設立し、そこからファンドを組成していくという形態をとることが一般的です。
投資事業組合は期限が設けられ、ファンドとして一般的な10年という期間がCVCでも採用されることが多くなっていますが、5年や7年などの期間を設定するケースもあります。いずれの場合も2年程度の延長期間を設ける点については、一般的なファンドと同様です。
CVCを運営する人員ですが、グループ内の人員で運営する方法や、専門家を採用して運営を委任する方法があります。
グループ内の人員に任せると、ファンドの経験者などでない場合にはファンドとしての活動が、スムーズにいかないリスクがあります。
逆に外部から経験者を採用してきた場合には、社風や社内文化に合致しなければ事業会社の担当者と円滑なコミュニケーションが取りづらくなってしまうというリスクがあります。
CVCのベンチャー投資について誰が決裁権を持つのか、という点も決めなければなりません。
CVC側である程度の決裁権を持つ場合には、機動的な投資活動が期待できます。親会社への申請をすることなく、有望と判断したベンチャー企業に投資できるからです。 ただし、親会社としては協業に積極的になれない投資先を選定してしまう可能性があります。
親会社の決裁を必要とする場合には、スピード感は損なわれてしまうこともあり得ますので、CVCのガバナンスをどのようにするかは慎重な検討が必要となります。

事業会社がベンチャー企業への出資を必要とする場合に、なぜ事業会社本体からの投資ではなくCVCを通して出資をするのでしょうか。
一つには事業会社としてのリスクヘッジの側面が考えられます。 ベンチャー投資は、ハイリスク・ハイリターンの投資です。
成功すれば事業会社自体の事業の成長に繋がり、IPOなどのエグジットが実現すれば大きな投資リターンも得られます。しかしIPOは狭き門であり、実現しない可能性が高いのが現実です。事業提携自体も、実態としては成功といえない結果になることもしばしばです
事業的に、投資活動的に、ベンチャー企業への出資が失敗に終わったと判断したとき、CVCを通しての出資であればワンクッション置くことができます。
ベンチャー企業への出資をする場合、機動性の確保も重要です。事業会社本体で投資の判断をする場合にはスピード感を持たせた意思決定ができない場合が多く、投資機会の逸失の可能性が高まってしまいます。
投資活動自体を専門のCVCに担当させることで、機動的な投資活動が期待できるのです。

CVCがベンチャー企業へ投資する際どのように投資先を見つけ、どのような判断で決定するのでしょうか。
まず、投資候補となるベンチャー企業を探す必要があります。
投資候補となるベンチャー企業が見つかったら、対象企業の調査(デューデリジェンス、DD)を開始します。財務DDも重要ですが、目的に応じてビジネスDDも重点的になされます。
そのため対象企業のヒアリングにはCVCの担当者だけでなく、本体の事業会社の担当者も同席することがあります。
ビジネスDDでは、事業会社のビジネスとのシナジー効果を得られるのかが検討されます。
時代に即したサービスを生み出せるのか、事業拡大ができるのか、などを調査します。 事業会社としては先進技術を、ベンチャー企業としては知名度や豊富なリソースを求めているのです。
双方のニーズが合致してシナジー効果が得られると判断されれば、業務提携に進む可能性が高まります。
ベンチャー企業への投資の目的に、オープンイノベーションも挙げられます。
双方から技術者や企画者を出し合い、共同研究などの活動を行って新たなプロダクトを生み出すことを目指す行為です。 大企業に所属する優秀な技術者でも、新たなプロダクトの企画が存在していなければプロダクトを生み出せません。
新たなソリューションを考案しているベンチャー企業でも、リソースが限られていればそれを実現することはできません。双方が補完しあって新たなプロダクトの創出を目指し、より強固な関係性でプロジェクトを進めるために業務資本提携を結ぶのです。
CVCがVCである以上、ファンドとしての投資利益(キャピタルゲイン)の獲得を目指します。
IPOが実現すれば株式の評価益が計上され、M&Aにより出資額よりも高額で売却が成功すれば株式の売却利益がプラスされます。
CVCの投資の目的に業務提携があるため、投資先の株式を保有し続けて関係性を維持するという判断をすることもあります。
ベンチャー企業への貸付はハードルが高くなっているため、ベンチャー企業に対しては出資をするという戦略が採られるケースが多くなっています。
銀行によるベンチャー企業への出資は直接投資ではなく、CVCを設立して投資をする形態が一般的です。
銀行系CVCの戦略としては、リード投資家の判断に追随するというやり方が多いようです。

上述のような目的をもって組成され活動するCVCには、特有の課題があります。
まず、CVCはファンドとして活動するものの、スピード感を持った投資活動ができないことがあります。
投資後に事業会社の担当者がベンチャー企業のスピード感についていけず、期待したシナジー効果が得られない場合もあります。
投資効果においても、一般的なVCとは異なるCVCならではの障害があります。
一般的なVCの場合は、成長の実現を重視し、ベンチャー企業の事業内容自体にはあまり要求をすることはありません。
CVCの場合は投資先と事業提携している以上、投資目的を実現すべくビジネス自体に要求してくることもあります。自社が投資をする理由となったビジネスに注力し、協業にも最大限の努力を要請します。
しかし、ベンチャー企業としては自社の利益の最大化が目的となります。また、中には自社に特定の企業の「色」をつけたくないと考え、株主としてのCVCの名前を前面に出さないことがあります。
CVCは業務提携を重視してベンチャー企業に投資し、事業会社本体の担当者がビジネス面を担当します。
しかし、担当者はベンチャー企業のスピード感には慣れていないこともあり、協業のスピードが遅れてしまうことがあります。また事業会社側の担当者が異動などで変更となり、一からのスタートとなってしまうケースも見られます。
事業会社の担当者としても、孤立してしまってプロジェクトに対するモチベーションが低くなってしまうということもあります。

経済産業省が日本ベンチャーキャピタル協会とともに2018年11月に行った調査をまとめた「我が国のコーポレートベンチャリング・ディベロップメントに関する調査研究 」をもとに、解説します。
日本におけるCVCファンドの規模は55億円以下が45%と、一番大きな割合を占めています。
次点が56~110億円の22%なので、過半数が100億円には届かない規模で運営されています。
CVCファンドがこれまでに投資した国内の案件数としては、5件以下が44%、6~10件が14%となっています。
CVCはVCと異なり、単純に利益を追求するのみでなく事業会社のビジネスの発展を目的として活動する側面があります。
今後のベンチャー業界の発展のためにも、さらなるCVCの活躍が期待されます。
なお、投資後の目線がズレないように投資契約書等の内容については、慎重に吟味することが求められます。