自国外の企業をM&Aする「クロスボーダーM&A」とはなにか解説しています。クロスボーダーM&Aの種類や特徴、目的やメリット、主な手法や手順、成功させるポイントやリスク(失敗する要因)に加え実際の事例も紹介します。クロスボーダーM&Aの実施を検討されている方は参考にしてください。
2021.12.23(最終更新日:2024.03.18)

自国外の企業をM&Aする「クロスボーダーM&A」とはなにか解説しています。クロスボーダーM&Aの種類や特徴、目的やメリット、主な手法や手順、成功させるポイントやリスク(失敗する要因)に加え実際の事例も紹介します。クロスボーダーM&Aの実施を検討されている方は参考にしてください。
2021.12.23(最終更新日:2024.03.18)

クロスボーダーM&Aとは、買収する企業または買収される企業のどちらかが海外企業となるM&Aを指します。クロスボーダー(Cross-border)を直訳すると「国境を越える」ですが、ビジネスにおいては「国際間で取引する」という意味になります。
日本でクロスボーダーM&Aが活発に行われるようになったのは1990年代頃とされています。2000年代半ば以降は市場の拡大が進み、近年では中小企業のクロスボーダーM&Aも増加傾向にあります。
出典:野村資本市場研究所公式サイト「わが国でも増加するクロスボーダーM&Aによるグローバル展開」
出典:経済産業省公式サイト「我が国企業による海外M&A研究会 報告書概要」
クロスボーダーM&Aは、買収する企業と買収される企業がそれぞれIN(国内企業)なのかOUT(海外企業)なのかによって以下のように分類されます。
| 種類 | 解説 |
|---|---|
| IN-OUT | 国内企業が海外企業を買収するM&A(買い手が国内企業、売り手が海外企業) |
| OUT-IN | 海外企業が国内企業を買収するM&A(買い手が海外企業、売り手が国内企業) |
| IN-IN | 国内企業が国内企業を買収するM&A(買い手も売り手も国内企業) |
近年、IN-OUTでは欧米企業を買収する例が増えています。OUT-INにおいては中国企業から買収される事例が多いですが、そもそもOUT-INの事例自体が減少傾向にあります。
出典:MARR Onlin(2022年11月号)「外国企業への売却(OUT-IN)による海外事業からの撤退動向」 アジアが半減。国別は中国が首位(1-9月期)
株式会社レコフデータが運営するMARR Onlineによると、日本における2021年のM&A件数は4,280件で、内訳としてはIN-INは3,337件、IN-OUTは625件、OUT-INは318件でした。
国内企業のM&Aが圧倒的に多いものの、IN-OUTやOUT-IN といったクロスボーダーM&Aも決して少なくありません。
IN-OUTがOUT-INの約2倍となっている要因としては、高齢化や人口減少の影響によって日本国内の市場が縮小すると考えられています。そのため事業規模を拡大するには海外市場を目指す必要があり、その方法の一つにクロスボーダーM&Aが挙げられているためです。
出典:MARR Onlin(2022年2月号)「2021年のM&A回顧(2021年1-12月の日本企業のM&A動向)」
海外展開を目指す会社は事業規模を拡大したいという目的を持っているため、クロスボーダーM&Aは、日本国内で完結するIN-INのM&Aと比べて規模が大きくなる傾向にあります。大企業を買収することによって、一気に規模を拡大することができるためです。
また、クロスボーダーM&Aでは、買収後のPMI(Post Merger Integration)に苦労する例が多くなっています。PMIとは、2社間の経営や業務を統合するためのプロセスを指します。国境を越えたやりとりだと、言語だけでなく風土や文化の違いなども考慮しなければなりません。
政治や治安が不安定な国でM&Aを実施する際、思いもよらないリスクが生じることもあります。そのような状況下では話し合いは難しく、意思決定に時間を要する場合があります。

ここでは、クロスボーダーM&Aを進めるにあたって、その目的とメリットについて解説します。
クロスボーダーM&Aは、企業がグローバル展開する一つの手段としても用いられます。
自社だけで一から海外進出を考える場合、海外で事業をするためのノウハウや事務所の準備、人材確保などの手間がかかります。すでに海外で事業を行っている企業を買収できれば、それらの手間を軽減できスムーズな海外展開が叶うでしょう。
日本国内ですでに成熟しているマーケットも、海外では未開拓であることは多くあります。クロスボーダーM&Aを実施して、競合が少ない海外でそれらの事業を展開できれば、大きな利益に繋がると考えられます。
クロスボーダーM&Aでは、事業を行う上でのコスト削減にも期待できます。
たとえば、日本よりも賃金が安い国に進出すると人件費を削減できます。原材料を海外から輸入している場合、海外現地に事業拠点を作れば、輸入する手間やコストを省き安く仕入れることができるでしょう。
もし日本より税率の低い国で事業を展開すれば、税負担も軽減することができます。
自社にはない技術やノウハウを保有している企業を買収できれば、日本にはない新たな製品の開発や事業コストを見直せる可能性があります。
自社が持っているサービスに買収先企業が提供するサービスを掛け合わせることでシナジー効果が生まれ、新たな事業のアイデアが誕生するかもしれません。
自社はもちろん、相手企業にとっても大きなメリットが期待できます。

クロスボーダーM&Aでは、三角合併、LBO(レバレッジド・バイアウト)といった手法を使うことがあります。これらの手法やメリットについて解説します。
日本の法律では、日本企業と海外企業の直接合併が認められていません。そのため、合併するには海外企業が日本に子会社を作り、その子会社がM&Aを実行するという手順を取る必要があります。日本企業と海外企業、そして海外企業の子会社の3社が連携してM&Aを行うことから、三角合併という名前がつけられました。
三角合併では海外企業が日本国内に100%の子会社を設置し、その子会社に自社株を渡します。合併が決定したら、日本企業の株主が持つ株式と子会社が持つ親会社株式を交換することでM&Aが成立します。海外企業は、買収先の日本企業を100%の子会社として保有できます。
自社の株式を用いることによって、買い手の海外企業が現金を用意せずにM&Aを実行できるのが、三角合併のメリットといえるでしょう。
LBO(レバレッジド・バイアウト)は、買収先企業の持つ財産や信用力を担保に金融機関などから借り入れを行い、その資金でM&Aを実施する手法です。
買い手の状態よりも買収先の信用力によって融資できるかどうかが決まり、借金返済も買収先の資産や収益によって行うため、限られた自己資金で大型のM&Aを実行したい場合によく用いられます。
また、借り入れた資金は利息をつけて返済する必要がありますが、その利息は経費とみなされるため、税負担の軽減も期待できます。
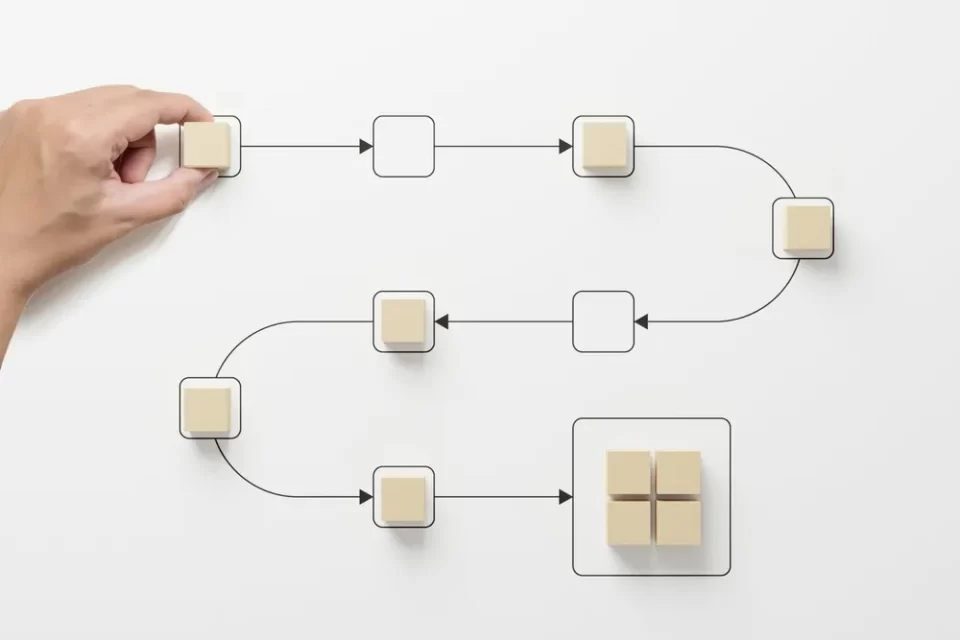
ここからは、クロスボーダーM&Aの手順と重視しなければならないポイントについて解説します。
クロスボーダーM&Aを検討する際には、国内でM&Aを行うとき以上に経営戦略を明確にさせておく必要があります。期待する効果や目的が曖昧なままでは、M&Aの実行自体がゴールになってしまう可能性があるためです。
まずは、自社の経営戦略や中長期のビジョンを明確にしましょう。M&Aがどのような効果をもたらすのか、海外企業と繋がることでどのような影響があるのか、具体的な分析が必要です。
メリット・デメリットも挙げ、クロスボーダーM&Aが自社の企業価値の向上に繋がるのか、十分に検討しましょう。
情報収集と企業選定を開始します。早い段階から現地に詳しい専門家とコンタクトを取り、海外の法律や政治、マーケットについて情報を集めましょう。
情報収集と調査のあとは、M&A相手の候補企業を挙げていきます。候補企業の選定は、クロスボーダーM&Aを行う上で重要なプロセスです。専門家と相談しながら企業の業績やビジョンを細かく調査・分析し、自社の目的に合った企業を絞りこんでいきましょう。
デューデリジェンス(買収監査)とは、買収先企業の実態を把握する事前調査を指し、クロスボーダーM&Aをする際の最も重要な手続きの一つと言えます。基本合意書を締結したあとに行うのが一般的です。
業績や収益力、法務、税務の実態などを調べ、買収するにあたってリスクがないことを確認しましょう。文化や価値観が異なる海外企業が相手のため、想定外のリスクが見つかる場合もあります。
一般的なデューデリジェンスでは、ビジネス、法務、財務、税務の4種類を調査します。調査にはそれぞれ専門知識が必要で時間もかかるため、弁護士や会計士、税理士などの専門家に対応してもらう必要があるでしょう。デューデリジェンスの種類と対応先は以下の通りです。
| デューデリジェンスの種類 | 対応先 |
|---|---|
| ビジネスデューデリジェンス | 買い手企業 |
| 法務デューデリジェンス | 弁護士(弁護士事務所) |
| 財務デューデリジェンス | 公認会計士(会計事務所) |
| 税務デューデリジェンス | 税理士(会計事務所) |
対応先については、主に以下の項目の確認・検証をして買収側企業にレポート報告するのが一般的です。
クロスボーダーM&Aでは、リスク回避に向けて特に入念なデューデリジェンスが必要となります。
デューデリジェンスと同時に、相手企業との交渉も進めていきます。文化や言語の違いによって認識の相違が生まれやすいため、できれば現地に足を運び対面で交渉する場を設けるといいでしょう。
初期の交渉では、M&Aを実行した場合に想定される事業シナジー等を議論することによって、両社の認識を見極めて意識を醸成するように努めることが肝要です。
相手企業との交渉が進み、諸条件で合意を得られたら契約を成立させます。海外企業とのやりとりで用いる契約書は英語で作成することが多いですが、場合によっては現地の言語で作成しなければならないこともあります。契約締結後の条件変更は難しいため、専門家に相談しながら細かく条項を確認していきましょう。
M&A契約が無事に締結されたら、続いてPMIの協議を行います。M&Aによって買収した企業は経営方針や業務の進め方、社風などが異なります。これらを互いに理解し合い、統一することでより良い関係性を築き、企業価値を高めるのがPMIの役割です。
海外企業とのM&Aにおいては、PMIに時間がかかり苦労する場合が少なくありません。契約締結前の段階からPMIについて協議できると、そのあとの動き出しがスムーズになるでしょう。

ここでは、クロスボーダーM&Aを成功させるために意識しておきたいポイントについて解説します。
M&Aの目的は、会社によって千差万別です。クロスボーダーM&Aの際は対象となる国に注目が行きがちですが、国や業種だけでなくM&Aの目的を達成するために対象会社の何が欲しいのかをより具体的に明確にしておく必要があります。
例えば、対象会社の製造設備、技術、IP資産、販売ネットワーク、仕入ルート、人材などが挙げられます。デューデリジェンスを行う際には当初の目的に立ち返り、その目的を果たすことができる企業なのか、改めてその対象会社を買収することによって何を獲得したいのかという視点で調査を行うとよいでしょう。
M&Aは実行すること自体が目的ではなく、複数の組織を統合して企業の価値を高める手段の一つです。そのため、企業価値を高めるにはPMIの成功が重要になります。
海外企業とのPMIは、より早い段階から具体的に計画を立てておきましょう。契約前にPMI協議を進めておけば、契約締結後に齟齬が生じるリスクを軽減できます。
クロスボーダーM&Aでは、必ずブレークアップフィー条項を締結しておきましょう。
ブレークアップフィーとは、何らかの事情でM&A契約が白紙になった場合に、売り手(買収される企業)が買い手(買収する企業)に支払う違約金を指します。買収価格の1〜5%に設定されることが一般的です。
クロスボーダーM&Aの実施においては、準備段階から多くの時間とコストを費やさねばなりません。契約が進まなかったときのリスクに備えて、必ず事前に締結しておくことをおすすめします。
M&Aの相手がリスクを抱えていないか調査するデューデリジェンスだけでなく、バリュエーションも重要です。
バリュエーションとは、企業の資産や知的財産などと将来性を加味して算出する企業価値です。この価値が算出できないと、自社の利益は上がらないどころか損してしまう可能性もあるため、現地の市場でどれほどの価値があるのかを算出する必要があります。
現地の情報を細かく調査した上で、実態に近い数値を算出しましょう。
クロスボーダーM&Aを進めるには、海外市場の事情把握から法律の知識、海外現地の文化や風土の理解、財務など幅広い専門知識が求められます。
クロスボーダーM&Aの成功のコツは、早い段階から専門家の力を借りることだといえます。M&A支援の実績が豊富で、かつ対象の地域に特化した専門家に依頼することをおすすめします。
AGSコンサルティングは、ASTHOMグループのメンバーファームとして11か国31か所に拠点を持っているため、様々な地域でのクロスボーダーM&Aを支援しております。気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

クロスボーダーM&Aは海外企業との取引のため、事前に想定しにくいリスクが存在します。それらのリスクについてそれぞれ解説します。
カントリーリスクは、その国の政治や経済、社会情勢が変化することによって起こりうるリスクです。
情勢が不安定になり金融市場に混乱が生じると、投資回収が困難になったり、売買代金の支払いができなくなったりしてしまう可能性があります。
政権交代や争乱により、海外との取引ができなくなるリスクについても理解しておく必要があります。
環境リスクは、国によって異なる環境への基準や規制に対応できなかった際に起こるリスクを指します。
日本より土壌汚染や水質汚染などに厳しい国は多くあるため、対策を怠ると厳しい罰則が科せられます。場合によっては、数億円にものぼる巨額の賠償金を請求されることもあります。
現地の環境リスクに精通した専門家に相談し、事前に環境デューデリジェンスを実施しておくとよいでしょう。
日本と海外では、訴訟に対する考え方が異なります。例えばアメリカは日本と比べて訴訟が頻発している訴訟大国であり、賠償金も日本より高い傾向にあります。訴訟への対応を間違えたことによって、倒産の危機にさらされる恐れもあるでしょう。
クロスボーダーM&Aを実施する前に、訴訟リスクに備えて現地の法制度や訴訟の考え方を把握しておきましょう。万が一訴訟を起こされた場合に落ち着いて対応できるよう、手順のシミュレーションをしたり、信頼できる弁護士を見つけたりして備えておくことが重要です。
労働文化や雇用制度は、国によって大きく異なります。
海外企業とのM&Aでは、雇用制度や考え方のすり合わせがうまくいかず、契約締結後の統合に失敗してしまうことが少なくありません。労働組合が中心となって、海外企業との統合に反対する事例もみられます。
このようなリスクを避けるには、相手国の雇用制度を深く理解するとともに、雇用者が納得できる説明をしなければなりません。

アメリカ市場は、世界最大級の市場の一つといえます。新たな顧客層へのアプローチや、ビジネス規模の拡大戦略としてアメリカ進出を視野に入れている日本企業も多いです。
自動車技術や半導体、医薬品、日本食などの技術や専門知識を持つ日本企業は世界から注目されています。そのため、アメリカ側も産業の進化やイノベーション促進を期待して、クロスボーダーM&Aが行われています。
アメリカのクロスボーダーM&A市場は、経済の変動と国際関係の影響を受けながらも、継続的な成長を遂げています。アメリカ企業は、利益につながる限りは積極的な姿勢を維持します。
アメリカ企業の成長と利益を追求し、企業が大きく成長するためにはM&Aが重要であるという認識が広がっています。また、不景気への備えとしても、M&Aによる企業体力の強化がみられます。
たとえば、AIやIoT、FinTechなどの先端技術に関連するM&A市場が今後拡大すると予想されており、これはIT分野の革新と企業の成長機会の両方を促進するものとなっています。アメリカでは小規模企業やスタートアップに関するM&Aが迅速に進行し、コストと時間を抑えることが可能なため、M&A市場は成長を続けています。
特に、米国市場では単純な海外展開という意味での新興国への投資と異なり、企業の成長機会を促す機会と捉え、大型での投資を含めた投資機会が多くある一方、米国での規制や米国での会計処理を理由として留意すべき事項も含まれています。
アメリカのM&A市場における課題としては、政治的な不確実性と厳格化する法規制が挙げられます。
2018年夏に始まった米中貿易摩擦では、2020年1月の第一段階合意によって事態の悪化は一時的に回避されました。しかし、米中関係が不安定である以上、貿易摩擦自体が解消したわけではありません。このような政治的不確実性は、アメリカのM&A市場において大きな課題といえるでしょう。安全保障等の観点からも、外国企業による投資に対する米国政府による審査は厳しくなっています。
日本と異なる規制は、政治的な背景にある法規制にとどまらず、米国証券取引委員会(SEC)の規則や会計処理といった点にも及びます。特別買収目的会社(SPAC)の新規株式公開と合併取引という異なる形態や、逆三角合併等の組織再編行為等、米国であるがために再編行為が異なることもあります。
加えて、米国では地域統括会社を中心とした孫会社の取得が多い一方、意思決定スピードが速く日本と異なる会計処理等、規制外での異なる会計や文化も見られます。米国に子会社を買収した後においても、ガバナンスを通じた適切な意思決定をモニタリングすることで、買収時想定したシナジー測定を定期的に行える体制構築も必要となる点にも留意が必要です。
会計・税務・法制度だけではなく、言葉・文化・商習慣の異なるアメリカ企業M&Aは留意点も多く、海外M&Aに精通した各種専門家との連携が必須となります。
米国の非上場企業には法定監査制度がないため、特に監査を受けていない中小規模の米国企業を買収する際は、デューデリジェンズで明らかになった会計・税務上の問題点や要検討事項について、取得後の対応方法を事前に検討し準備する必要があります。まずは、財務デューデリジェンスで修正が必要と指摘された会計処理について、取得日時点の財務諸表への影響を明確にし、BS・PLを確定する必要があります。
また、取得後には既存の経理体制で日本企業が求めるレベルでの決算や報告スケジュールへの対応が可能か、税務についてはこれまでの対象企業の顧問税理士が国際間取引に関する税務コンプライアンスに精通しているか、今後も顧問を任せられるかどうかなどの検討も必要です。日本企業が主導する海外M&Aでは、日本語の通じる現地会計士や税理士によるサポートは、M&Aプロジェクト推進を円滑に行うための大きなベネフィットになりえます。
M&Aにおいて会社を買収した際の取得原価を、買収した資産負債に配分する手続きが必要になります。取得価格と買収した資産負債の評価額との差がのれんとして評価されます。PPAでは、元々対象会社の資産負債に計上されていない技術やブランド、ノウハウといった無形資産も評価対象になりえます。
米国企業を買収する際に、日本企業が直接持分を取得するのではなく、米国内にBlocker Corporationと呼ばれる特別目的会社を設立して、そのBlocker Corporationを通して買収する場合がありますが、このような場合、米国会計基準にはみなし取得日の概念がないため、取得日時点において上記のような無形資産も含めて識別可能な資産負債の時価評価を実施する必要があります。
買収する米国企業がJ-SOXの評価対象拠点に入るかの検討と、評価拠点となる場合は評価対象範囲、プロセスをグループ監査人に相談するなど、事前準備が必要です。デューデリジェンスを通して理解した現状の内部統制状況を分析し、具体的にどのような管理体制を構築・運用していくか、買収後のJ-SOX導入までの計画を立てます。
日本とは異なる制度や商習慣への対応が必要となるため、海外においてJ-SOXに精通した人材または信頼できる外部専門家の確保も重要な課題となります。
外国企業が米国法人に一定金額以上の直接・間接投資をする場合や、外国法人が米国内に新たな法人を設立するような場合、米国商務省の一機関である経済分析局(BEA)への報告が義務付けられています。アメリカ合衆国が米国経済に関する重要な統計を提供することを目的とした機関で、米国企業に対して様々な財務情報や外国取引に関するデータの提出を義務付けています。米国企業を買収する場合、買収後速やかに専門家に相談し、対応する必要があります。
2024年1月1日に発効した企業透明化法(CTA)は、マネーロンダリング、テロ資金調達、その他の違法な資金調達に対処・防止することを目的として、新た特定の事業体(主に中小企業)に対し、会社の「実質的所有権」に関する情報(Beneficial Ownership Information)を米国財務省金融犯罪捜査網(FinCEN)に報告することを義務付けています。米国企業の買収により、日本企業が実質的所有権を持つ場合、買収後速やかに専門家に相談し、対応する必要があります。CTAの報告対象企業が報告を怠った場合は、ペナルティーや罰則があるため、買収前の対象企業のコンプライアンスの遵守状況を把握することも重要です。

日本企業にとって同じアジア圏のM&Aは、比較的ハードルが低いという見方もあります。特にシンガポールは安定した政治や緩和された外資規制、法人税率の低さなどで、M&A先として注目されています。
今のシンガポールは日本と同じく、後継者不足による事業承継が課題となっています。移民が多く親日感情を持つ方も多いことから、日本企業を受け入れる土壌が整っているのも特徴です。日系企業によるASEAN企業の買収案件でシンガポールの比率が高い現状が今も続いております。
また、シンガポールはASEANのハブとしてASEAN域内の関係会社を統括する地域統括会社を設置している会社が多く存在します。シンガポールだけでなくASEAN市場への進出を目指す日系企業にとってもシンガポールに存在する地域統括会社を買収することによってASEAN域内のビジネスを丸ごと買収できるというメリットがあります。
シンガポールのM&A、特に中小規模の売出し情報はまだ広く認知されておらず、現地の事業承継ニーズと買い手としての日本企業をつなげるサポートが重要になっています。

日本企業が海外企業を買収するIN-OUTのクロスボーダーM&Aについて、具体的な例を紹介します。
2021年7月、日立製作所はアメリカに本社を置くIT企業・グローバルロジックを約1兆円で買収したと発表しました。日立製作所が開発したIoTプラットフォーム「Lumada」を世界に広めるための買収でした。グローバルロジックが抱える顧客基盤を手に入れることにより、グローバル市場でのビジネス展開を拡大させる目的のM&Aです。
日立製作所の買収方法は「逆三角合併」と呼ばれます。これは、相手企業を自社に合併させるのではなく、相手企業が自社の親会社となる合併方法です。相手企業が存続するため、技術やスキルを取り入れやすいというメリットがあります。
出典:株式会社日立製作所「日立が米国GlobalLogic社の買収を完了」
2021年4月、パナソニックはアメリカ・ブルーヨンダー社の株式を取得し、完全子会社化したと発表しました。
ブルーヨンダーは、サプライチェーン管理効率化のためのクラウドサービスを提供するソフトウェアの会社です。サプライチェーンマネジメントは変化が速い業界とされており、そのスピードに対応するためM&Aが行われました。一から仕組みを開発するのではなく、アメリカですでに開発が進んでいるものを取得した方が良いと判断されたのです。
また、パナソニックの得意分野であるセンシングやロボティクス分野のハードウェアと、ブルーヨンダーの得意分野を掛け合わせることで、これまでにないソリューションを生み出すことも期待されています。
出典:パナソニック株式会社「世界トップクラスのサプライチェーン・ソフトウェアの専門企業であるBlue Yonderの全株式取得を決定」
2021年7月、ルネサスエレクトロニクスはイギリスのダイアログ社を6,157億円で買収したと発表しました。
ダイアログ社は、電源制御ICや充電制御IC、低電力通信ICなどを生産する半導体メーカーです。このM&Aによって、ルネサスは自社のMPU・MCUと組み合わせ、新たなソリューションを提供することが可能になりました。
また、会社の規模が大きくなることで、材料費などの調達費を削減する効果も期待されます。
出典:ルネサスエレクトロニクス株式会社「ルネサスがDialog社の買収を完了」

企業の価値向上が期待できるクロスボーダーM&Aですが、実際に取り組むにはさまざまな分野の専門知識や経験が必要です。
M&Aで実現したいことを明確にし、そのゴールに向かって企業選定や交渉を行うよう意識しましょう。また、早い段階から専門家に頼ることでトラブルやリスクを避けてスムーズにM&Aを実行できます。