消費税とは、商品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金のことですが、シンガポールにもGSTという消費税と類似した仕組みがあります。今回はそんなシンガポールにおけるGSTについて、日本の消費税制度と比較しながら解説していきます。
2022.06.03(最終更新日:2024.01.31)

消費税とは、商品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金のことですが、シンガポールにもGSTという消費税と類似した仕組みがあります。今回はそんなシンガポールにおけるGSTについて、日本の消費税制度と比較しながら解説していきます。
2022.06.03(最終更新日:2024.01.31)

シンガポールにおける財・サービス税(Goods & Services Tax:GST以下、GST)は日本でいうところの消費税にあたり、1994年4月1日に導入された税制度です。
2007年7月1日から GST の標準税率は7%に制定されています。ただし、今後9%に増税することがシンガポール政府から公表されています。
シンガポールにおけるGSTは、日本の消費税同様、売上に係るGSTから仕入に係るGSTを控除した差額を納付、または還付を受ける仕組みです。
また、GST制度での課税方式はインボイス方式になる点が、日本の消費税の納税制度と異なっています。
インボイスとは、「登録番号、適用税率、税額などの要件を満たした請求書、もしくは納品書」を指します。そして、インボイス方式とは、その請求書によって税金を計算して納付する制度のことです。
具体的には、売手である登録事業者が買手である課税事業者に対してインボイスを発行し、それに記載されている税額のみ控除して課税する、といった方式になります。
企業が顧客にGSTを請求する際は、TAX Invoice(日本で言う請求書)に上述の要件を記載し、決められたフォーマットで請求と保存をする必要があります。
シンガポールでは課税事業者となることが認められるまではTax Invoiceを発行できないため、届出が遅れると、そのままGSTの請求漏れが生じて会社に損失が発生することになります。正しい届出のタイミングを把握することが重要です。

GSTは登録制であり、登録企業だけにGSTの申告義務があります。そのため、未登録の企業は顧客に対してGSTを請求できません。
GSTの制度上、年間の課税売上高がSGD1,000,000超の企業は内国歳入庁(IRAS )にGST登録を行い、自社商品やサービスを国内で販売や提供する際にGSTを課す義務が生じます。
なお、年間課税売上高がSGD1,000,000以下の企業でも、任意でGST登録が可能です。任意登録によってGSTの還付を受けられ、有利になることもあります。
ただし、任意登録には一定以上の銀行からの保証が必要となる場合もあるため、その条件も含めて任意登録の必要性を検討することとなります。
GST登録企業は、登録前に商品およびサービスの購入で発生したGSTについて、登録後に使用された商品・サービス、あるいは課税対象物の生産のために使用されたとみなされる部分だけを控除して還付申請ができます。
一方で、課税売上がSGD1,000,000を超える場合でも、そのほとんどが0%課税売上の場合にはシンガポール税務当局に申請し承認を得ることで、課税事業者の登録の免除を受けることが出来ます。

海外への輸出や一定の国際サービスを除き、原則、シンガポールでの財貨およびサービスのすべてがGSTの課税対象となります。
一方で、シンガポール国外で行われるいわゆる三国間貿易や金融サービス、住宅用不動産の販売・レンタル、金などの取引は課税対象外です。
シンガポールからの輸出において課税対象となるケースや、通関時点でほとんどの商品にGSTが徴収されるシンガポールへの輸入については注意が必要です。
上記のように原則として課税取引である一方、下記のような取引では、申告を条件にシンガポールの政策的観点から非課税となります。
銀行手数料、為替換算手数料、クレジットカード手数料、有価証券やビジネストラスト受益権、イスラム債等の発行や譲渡取引、信用貸付や分割支払い手数料などは非課税取引とされます。
一方、保険の仲介手数料等のブローカー報酬やアドバイス報酬は課税対象です。
居住用の土地や居住用物件の譲渡および賃貸料は非課税取引とされます。
一方、物件と共に貸し出される家具等の賃料や物件の仲介料、アドバイス報酬等は課税対象です。
金や銀、プラチナなど、市場価格が存在して流動性の高い貴金属は、金融商品に似た性質であるとして非課税取引とされています。
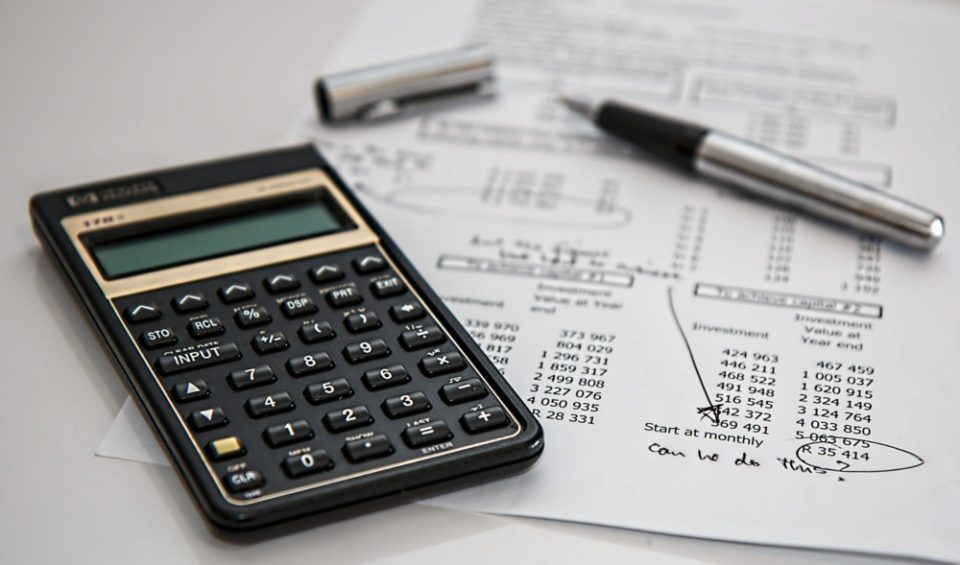
シンガポールGSTの納税金額は、課税売上にかかるGST(Output GST)から、課税仕入にかかるGST(Input GST)を控除して計算します。
日本における消費税計算のように、課税売上割合に応じた課税仕入にかかるGSTの控除額が制限されることはありません。ただし、自社宛に発行された有効なTax invoiceの裏付けがなければ、課税仕入れにかかるGSTを控除することは出来ないため、留意が必要です。
シンガポールGSTの納税金額は、課税売上にかかるGST(Output GST)から、課税仕入にかかるGST(Input GST)を控除して計算します。
日本における消費税計算のように、課税売上割合に応じた課税仕入にかかるGSTの控除額が制限されることはありません。ただし、自社宛に発行された有効なTax invoiceの裏付けがなければ、課税仕入れにかかるGSTを控除することは出来ないため、留意が必要です。

GST登録会社は、原則として四半期ごとにGSTの計算結果を電子申告・納付する必要があります。ただし、還付が毎回発生するような企業は毎月申請をすることもできます。
申告・納付期限は、各四半期の計算期間終了日から1ヶ月以内です。例えば、12月決算法人の場合、1~3月までの期間に係るGSTを4月末までに申告することとなります。

ここまででシンガポールGST制度について税務上の基礎的な事項を解説してきました。
ここからは、今後の法改正等、税務上の重要なポイントを解説します。
ほとんどの商品については、輸入された時点でシンガポールの税関にてGSTが徴収されることになります。一般関税または物品税などの課税対象品目を輸入する場合も、GSTはそれらの税金とともに徴収されます。
一方、輸出品と国外向けのサービスは、GSTが徴収されません。また、国内で調達した商品を輸出するGST登録事業者は、国内で支払ったGSTを還付請求できます。
2018年の税制改正によって、2020年1月以降はサービス輸入に対してGSTが課税され、シンガポール顧客向けにデジタルサービスを提供する海外事業者は影響を受けることとなりました。
シンガポール政府が発表した2021年予算案において、2023年1月1日から、航空便や郵便でシンガポールに輸入され、シンガポールの消費者がGST登録業者から購入する低額商品(SGD400以下の商品)にもGSTが適用されることとなりました。
現状、シンガポール国内で調達された低額商品にはGSTが適用されていますが、海外から調達して航空便や郵便で輸入された同じ商品には、GSTが適用されていません。
この変更は、シンガポール国内で調達されたもの、もしくは海外から調達されたものかにかかわらず、シンガポール国内で消費される全ての商品に対し、GSTの扱いを公平にすることを目的としたものです。
上記に加え、2023年1月1日以降はGSTに登録された海外のサービスプロバイダーから購入した非デジタルサービスの輸入にもGSTが適用されることになります。現在GSTの対象となっているデジタルサービスは引き続き課税対象です。
つまり、デジタル・非デジタルを問わず、遠隔地で提供・受領できる輸入サービス(リモート・サービス)の提供はすべてGSTの対象となることに留意が必要です。

シンガポールのGST制度について、税務上のポイントを日本の税制との比較を交えて解説しました。
税務知識はその国でビジネスをする人にとって必須の情報です。シンガポール進出を検討する際は参考にしてみてください。