株式移転とは組織再編の手法の一種で、既存の株式会社が新規に親会社を設立することを指しますが、株式移転が有効なケースや手続きについて分からない方も多いのではないでしょうか。この記事では、株式移転の概要やメリット・デメリット、手続きの流れなどを解説します。会社の組織再編を検討中の方はぜひ参考にしてください。
2022.07.21(最終更新日:2024.02.01)

株式移転とは組織再編の手法の一種で、既存の株式会社が新規に親会社を設立することを指しますが、株式移転が有効なケースや手続きについて分からない方も多いのではないでしょうか。この記事では、株式移転の概要やメリット・デメリット、手続きの流れなどを解説します。会社の組織再編を検討中の方はぜひ参考にしてください。
2022.07.21(最終更新日:2024.02.01)

最初に、株式移転の概要や組織再編における位置づけなどについて解説します。
株式移転とは、既存の株式会社(1社または複数)が新規に親会社を設立して、発行済株式を全て取得させる組織再編の手法のことで、M&Aのシーンでも活用されています。
この株式移転によって完全な親会社子会社の関係が構築できます。
株式移転には複数の株式会社が子会社になる経営統合のパターンと、1つの株式会社単独で行う持株会社(ホールディングス)化のパターンがあります。
複数の株式会社が共同で株式移転を行い、発行済株式の全部を新設会社に取得させる手法を「共同株式移転による経営統合」といいます。
共同株式移転により、既存の会社は新設会社の子会社となります。 それまで個別に営業していた会社同士が経営統合する場合、それぞれの社風や商習慣の違いなどが影響して、成功しない可能性があります。
一方、共同株式移転では、既存の会社は存続するため、経営統合後の役員や従業員の心理的抵抗が少なくなることが考えられます。
持株会社(ホールディングス)化、つまり1社単独での株式移転では親会社となる持株会社を新設し、既存の会社の全発行済株式を取得させます。
多くの場合、持株会社化は所有(株主)と経営(役員)を分離することで、事業の健全運営を目指す目的で実行されます。
また、結果的に株価対策に繋がる側面を持ち合わせています。
グループ再編には、複数の会社の統合や既存の会社を買収するなどの手法があり、自社の目的に合った手法を見極める必要があります。
会社法に規定されているグループ再編の手法には、「合併」「株式交換」「株式移転」「会社分割」の4種類があります。
| 手法 | 説明 |
|---|---|
| 合併 | 2つ以上の企業が合体して、1つの企業になること |
| 会社分割 | 企業の一部の事業を自社から分割し、ほかの会社に総合的に承継すること |
| 株式交換 | 完全子会社となる会社の発行済株式を親会社となる会社に譲渡し、完全親会社となる会社は対価として自社の株式を完全子会社となる会社の株主に割り当て、親会社・子会社の関係を構築すること |
| 株式移転 | 完全子会社となる会社の株式を新設した完全親会社となる会社に譲渡し、完全親会社となる会社は対価として自社の株式を完全子会社となる会社の株主に割り当てること |
いずれも企業買収で用いられる手法で、株式交換・株式移転では既存の会社は再編後も存続します。
これに対し、合併では1社のみが存続し、他の会社は消滅します。
会社分割では、事業部門を他社が引き継ぐため、分割元の会社も存続します。
上述したように、株式移転と株式交換は、ともに親会社・子会社の関係を構築するグループ再編の手法であり、類似しています。両者の違いは、株式移転では親会社を新設するのに対し、株式交換では既存の会社を親会社とする点です。
効力発生日も異なり、株式移転では新設会社の登記日に効力が発生し、株式交換では株式交換契約書にて記載された日に効力が発生します。一般的に、株式移転はグループとしての組織再編に重きを置いて実行しますが、株式交換はグループとしての組織再編に加えて、他社の買収を目的としても実行されるという違いがあります。

組織再編の手法によって得られるメリットが異なるため、他の手法とも比較して、株式移転が自社に適しているかを考えましょう。
株式移転のメリットは、主に以下の通りです。
株式移転による組織再編では新設の親会社が株式移転の対価として新株を発行すればよいため、取得のための資金が必要ありません。
通常の買収の場合、対象企業の株式取得のための資金が必要で、規模によっては高額になる可能性もあります。
一方、株式移転では、会社の財務への影響なしに組織再編が可能です。
株式移転による組織再編が行われても既存企業は子会社として存続するため、早急な改変をしなくても事業を継続できます。
グループ全体の内部統合は時間をかけて行えるため、大きな混乱に伴うリスクを避けられます。
株式移転には税務上、「適格株式移転」と「非適格株式移転」に分かれます。適格株式移転に該当すると資産の移転が簿価で計算され、評価損益を計上せずに課税が繰り延べられます。
適格株式移転では一定の要件を満たす必要がありますが、完全親子関係を作れる株式移転の多くは適格株式移転に該当します。
株式移転では新設会社が子会社の全株式を取得するため、少数株主(親会社以外の株主)がいなくなります。
少数株主が経営方針に反対することで、事業推進の妨げになるケースもあります。少数株主が排除できるのは、株式移転の大きなメリットです。
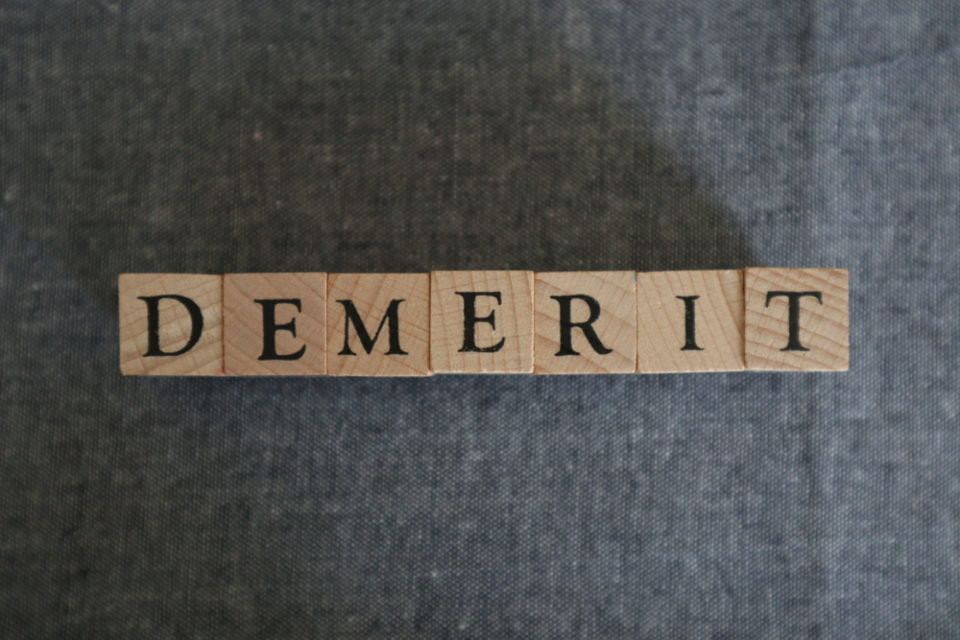
株式移転は、金銭の負担なく実質的な企業買収が可能などのメリットがありますが、組織再編の選択肢として検討する場合、デメリットも併せて押さえておきましょう。
株式移転で把握しておくべきデメリットは、主に以下の4点です。
株式移転では、株式移転計画の立案から株主総会での承認、反対株主の株式買取請求への対応などさまざまな手続きが求められます。
加えて、それぞれの手続きが煩雑であるため、一定の知識と時間もかかります。
着手から完了までに1カ月以上の期間を要するため、手続きに着手する前に綿密なスケジュールを立てて、計画的に実行する必要があります。
株式移転において、株主総会の開会前、並びに株主総会でも反対の意思表示をした株主は、株式買取請求権を行使できます。
株式の買取については会社と反対株主間で価格を協議して、合意した金額を支払わなければなりません。
共同株式移転の場合、複数の会社の株主が新設親会社の株主となるため、株主構成が変動します。
株主構成の変化は議決権に関わるため、経営上の意思決定に影響し、共同株式移転前の意思決定フローから大幅な変更が行われる可能性があります。
株式移転の買い手が上場企業の場合、株価が下落するリスクがあります。
1株あたりの利益が減少し、子会社を傘下に持つ=会社数が増加することによって管理コストが増加し、利益減少に拍車をかけてしまいます。
このような株価下落リスクによる株主の反対が想定される場合、株式移転のメリットを丁寧に説明する必要があります。

株式移転には、会社法に基づいた手続きが必要です。
株主総会の特別決議で株主の承認を得なければ、親会社の設立はできません。
株式移転の手続きは、以下のような流れで進めます。
株式移転では、最初に「株式移転計画」を作成します。
会社法で定められている、計画書に盛り込む主な項目は以下の通りです。
株式移転により完全子会社となる会社は、「株主総会の2週間前」など会社法で定められた日から新設会社が設立された日以降6カ月を経過するまでの間、事前開示書類を備え置かなければなりません。
事前開示書類に記載する主な内容は、以下の通りです。
株式移転をする会社は、株主総会の特別決議による承認を得る必要があります。
株主総会で承認されたら、新会社設立の登記申請を行います。登記申請時には主に以下の書類を添付します。
通常の会社設立では、株主資本のうち資本金の2分の1以下を資本準備金として計上できるルールがあります。
しかし、株式移転では変動した株主資本の範囲内で完全親会社の資本金・資本準備金などを任意で割り振ることができます。
また、登記にあたって、完全親会社の資本金に0.007を掛けた金額の登録免許税が必要です。
もしこの金額が15万円未満の場合は、一律で15万円となります。
株式移転では、新設する親会社の登記により効力が発生します。
株式移転の登記申請を行った日が効力発生日です。
株式移転の効力発生日以後、親会社と子会社は遅滞なく法務省令で定められた事項を記載した書面(事後開示書類)を作成します。事後開示書類は効力発生日から6カ月間本店に備え置く必要があります。
事後開示書類に記載するのは、以下のような内容です。

株式移転をするのであれば、適切な会計処理も必要になります。
ここでは、株式移転の会計処理(仕訳)について解説します。
株式移転では、当事者の立場によって仕訳が異なります。
株式移転で新設された完全親会社では、新株発行による資本金と資本剰余金の増加や、子会社株式の取得についての会計処理が必要です。
このとき、子会社が「取得企業」か「被取得企業」かで評価方法が異なります。取得企業の株式は取得前日簿価と、直前の決算時の簿価によって評価します。
一方、被取得企業の株式は、被取得企業の株主が保有する議決権比率と同じ比率を、新設会社に交付したとみなして評価します。
M&Aにおける企業結合取引では、取得企業と被取得企業を判定します。
株式移転の場合、新設される親会社は取得企業とはなりません。
そこで、完全子会社となる会社のなかで取得企業、被取得企業を判定します。
株式移転の取引は、既存会社の株主と新設会社間で行われます。
完全子会社は取得企業・被取得企業を問わず、原則として会計処理は発生しません。
以上は株式移転の基本的な仕訳処理ですが、例外も存在します。
親会社・子会社間の取引など、トップの株主が共通する会社同士の取引を「共通支配下の取引」といいます。
親会社・子会社関係だった会社同士で株式移転を行う場合、新設会社の仕訳は以下の通りです。
株式移転前に親会社だった企業の株式取得については、株式資本の適正な簿価で会計処理をします。
株式移転前に子会社だった企業の株式取得については元親会社の100%子会社の場合、株式資本の適正な簿価で会計処理をする決まりです。
元親会社の100%子会社でない場合、元親会社の保有分は株主資本の適正な簿価に元親会社持ち分比率を掛けた金額で評価します。
他の株主の持ち分については、先述した被取得企業株式と同様に評価します。
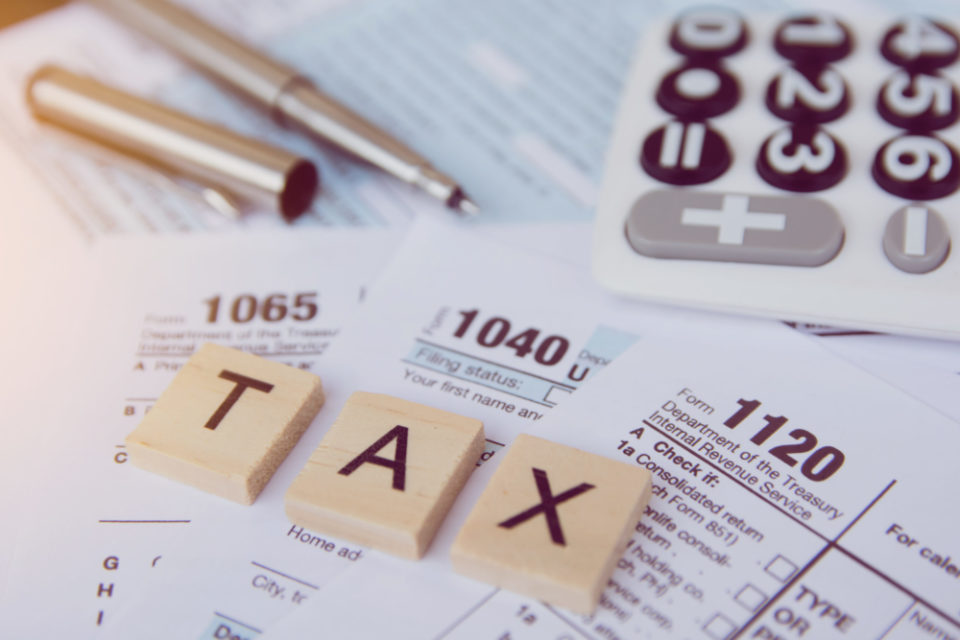
組織再編の資産移転で発生する譲渡益には税法上、課税されるのが原則です。
しかし、そのために有益な組織再編を行えなくなるおそれがあります
そのため、一定の要件(適格要件)を満たす株式移転などの組織再編は例外的に扱われる「組織再編税制」が適用されます。
株式移転では、適格要件を満たすか満たさないかで、税務が変わります。
適格要件を満たして適格株式移転と判定されれば、完全親会社と完全子会社、完全子会社の旧株主には課税が繰り延べられます。
適格要件株式移転とみなされる場合で、完全親会社における完全子会社株式の取得価額の評価方法は以下の通りです。
なお、完全子会社に必要な税務はありません。
非適格要件株式移転とみなされる場合で、完全親会社における完全子会社の株式の取得価額は完全親会社設立日の時価を用います。
完全子会社では資産の一部を時価評価し、損益算入をしなければなりません。
上述した株式移転の適格要件とは、株式移転の際に課税が繰り延べられる条件のことで、株式移転を行う会社同士の関係によって変わります。会社同士の関係とは、以下の3種類です。
株式移転における会社間の関係ごとの適格要件は以下の通りです。
| 会社間の関係 | 要件内容 |
|---|---|
| 完全支配関係 |
|
| 支配関係 |
|
| 共同事業 |
|

株式移転では追加の手続きが必要になるケースがあるなど、関連する法律に注意が必要です。
株式移転を検討する場合、押さえるべき注意点を解説します。
株式移転は、株式会社しかできません。特例有限会社も株式を発行していますが、株式移転で完全子会社にはなれません。特例有限会社が株式移転で完全子会社になるには、組織変更により株式会社になる必要があります。
複数社の株式移転で以下の両方の条件に該当する場合、事前に公正取引委員会への届出が必要です。
株式移転では完全子会社となる会社は存続するため、権利義務の承継が生じません。よって、原則として債権者保護手続きは不要です。
債権者保護が必要となるのは、完全子会社の新株予約権付き社債の社債権者に対してとなります。
債権者保護手続きとしては、1カ月以上の請求期間を設けて以下の手続きを行います。
金融商品取引法において、次のような条件を満たす場合は有価証券届出書または臨時報告書を内閣総理大臣に対して提出しなければなりません。
株式移転は大きな費用負担なしに組織再編ができるため、メリットが大きい組織再編のスキームです。
しかし、実行にあたっては注意点もあり、手間や時間のかかる手続きが必要です。
組織再編を検討する際には自社で活用できるスキームの特色を比較し、どの手法が最適かを見極めてください。