株式会社などの営利を目的とする会社と異なり、営利を目的としない法人を「非営利法人」と呼びます。非営利法人にも、さまざまな種類があるのです。今回は、一般法人や公益法人といった非営利法人の違いや公益法人の運営、会計、税務について解説します。
2021.12.27(最終更新日:2024.01.31)

株式会社などの営利を目的とする会社と異なり、営利を目的としない法人を「非営利法人」と呼びます。非営利法人にも、さまざまな種類があるのです。今回は、一般法人や公益法人といった非営利法人の違いや公益法人の運営、会計、税務について解説します。
2021.12.27(最終更新日:2024.01.31)

社団法人と財団法人の組織は似ていますが、主に以下の5つの点で違いがあります。
一般社団・財団法人とは、一般法に基づいて設立された法人です。
行政庁の認可を必要とせず容易に設立でき、事業内容も特段制限がありません。
人(社員)の集まりに、法人格を与えたものです。社員総会が最高意思決定機関となり、社員からの会費が主な財源となります。
設立にあたって財産の拠出は要請されていませんが、活動の原資となる資金の調達手段として「基金制度」が設けられています。
「基金」とは、一般社団法人に拠出された金銭とそのほかの財産で、拠出者に対して返還義務を追うものです。
財産の集まりに、法人格を与えたものです。基本的には、当該財産の運用益が主な財源と考えられます。設立にあたっては、300万円以上の財産を拠出しなければなりません。
設立後も一定規模の財産の保持義務が課されるため、2期連続で純資産が300万円を下回る場合には、解散しなければなりません。 それぞれの違いは、以下のとおりです。
| 社団法人 | 財団法人 | |
|---|---|---|
| 機関設計 | ・社員総会(2名以上) →最高意思決定機関 ・理事会(3名以上) →理事会を設置しないことも可能 ・監事(1名以上) ・会計監査人 →条件を満たす場合には設置が必須 | ・評議員会(3名以上) →理事会を監督する機関 ・理事会(3名以上) ・理事(1名以上) ・会計監査人 →条件を満たす場合には設置が必須 |
| 成り立ち | 「人」の集まり | 「財産」の集まり |
| 財源 (主なもの) | ・会費収入 ・運用益等 ・事業収益 | ・運用益等 ・事業収益 |
| 設立時の拠出金 | 定めなし | 300万円以上 |
| 資金調達制度 | 「基金制度」あり (設置は任意) | 定めなし |
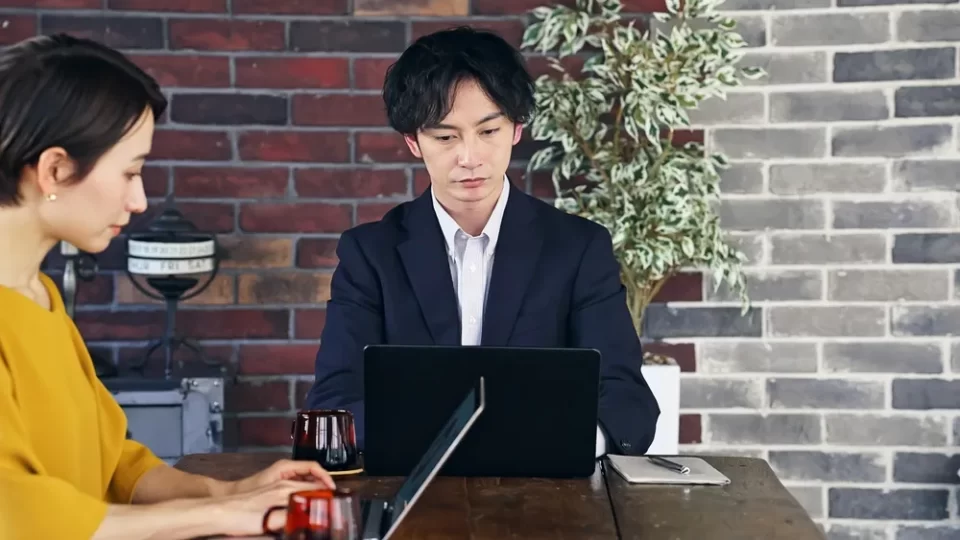
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、一般法)に基づいて設立された法人のことです。
一般法人は登記のみでの設立が可能なため、容易に設立できます。公益的な事業はもちろん、共益的なものや収益事業のみを行うことも何ら妨げられません。
共益的な事業とは、町内会や同窓会、サークルのように構成員に共通する利益を図ることを目的とするものです。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(以下、認定法)に基づいて設置される法人です。 公益法人は2階建ての制度といわれており、1階が一般法人、2階が公益法人を指します。一般法人を前提としているため、公益法人をいきなり設立できません。 公益法人となるためには、一般法人の設立後に公益認定の申請を行い、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の認定を受ける必要があります。
公益法人は、公益性の高い法人として税制上の優遇措置を受けられますが、将来にわたって公益認定の基準を満たす必要があります。公益認定の基準を満たせなくなると認定を取り消されるリスクもあるので、留意が必要です。
Non-Profit Organizationの略称です。さまざまな社会貢献活動を行い、構成員に対して収益の分配を目的としない団体の総称です(内閣府HPより)。 「特定非営利活動法人(NPO法人)」は、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人になります。
NPO法人を設立するためには、都道府県または政令指定都市の所轄庁に申請をして設立の「認証」を受けることが必要です。認証後、登記をすると法人として成立するので、ほかと成り立ちが異なります。
また、どちらも公益性を目的としていますが、NPO法人は20種類の分野に該当する活動が対象です。公益法人は23種類の事業を対象としているため、NPO法人とは異なります。
国や地方自治体の機関、国際機関などで働いている人のことです。
共通するのは、公益性を重視する点です。「公務員」が所属する組織は国や地方自治体が運営していますが、「公益法人」は民間の組織である点が異なります。

認定法上における「公益」は、以下の要件を満たす必要があります。
「公益に関する事業」かどうかは、認定法別表に列挙されている23の事業に該当している必要があります。
引用:認定法別表第二条関係
寄与しているか否かの判定については、内閣府公益認定等委員会が公表している「公益認定等ガイドライン」に記載されています。
公益法人が行う事業の中から典型的な17事業について、それぞれ具体的に掲げられています。
共通して求められる主なポイントは、以下の2つです。
不特定多数性の条件として、「社会全体に対して利益が開かれている」と「受益の機会が一般に開かれている」の2つを満たす必要があります。
公益認定の申請を行うためには、認定法第5条で定められた下記の要件(18項目)を満たす必要があります。
また、公益法人は認定を受けた後も、毎期認定基準の遵守が必要です。

社団法人と財団法人は類似した組織であり、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」という法律の中で規定されています。
共通する部分については、財団法人は社団法人の条文を準用します。
そのため、公益法人の運営・会計・税務については、社団法人と財団法人に共通する事項として、説明します。
公益法人は公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人ですが、公益目的事業以外の収益事業等を行えます。
公益目的事業は認定法において「学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する」事業と定められています(認定法2①四)。
公益目的事業以外の事業をいいます。利益をあげるための収益事業と、共益のためのその他の事業に区分されます。
収益事業は、一般的に利益をあげることを性格とする事業です。その他の事業は、一事業として取り上げる程度の事業規模や継続性がないものや、法人の構成員を対象として行う相互扶助などです。 収益事業などには公益目的事業のようなチェックポイントの要件はありません。
一方で、「収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれのないものであること」(認定法5七)という要件があります。収益事業などで大幅な赤字といったものが生じることによって、公益目的事業の実施に支障が出ないように留意する必要があります。

非営利法人は、公益法人会計基準が適用され、認定法で定める認定基準を満たす必要があります。
その中でも特に重要となるのが、財務3基準(収支相償・公益目的事業比率・遊休財産額の保有制限)と呼ばれる財務基準です。
公益法人が作成しなければならない財務諸表等は、以下のとおりです。
基本財産とは、法人の基本となる財産です。法人の定款において、基本財産として定められた資産のことをいいます。
特定財産とは、特定の目的のために使途、保有又は運用上の制約が課されている資産です。
指定正味財産とは、寄付によって受け入れた資産のことです。寄付者などの意思により、当該財産の使途について制約が課されています。
一般正味財産とは、法人の財産的基礎を示す正味財産のうち基金および指定正味財産を除いた部分です。
法人設立以後の事業運営により発生したすべての収益・費用などを加減算した、累積金額となります。
認定法上の公益法人と法人税法上の公益法人等は似ている用語ですが、意味は異なります。
法人税法上の公益法人等は、法人税法別表第二に掲げる法人を意味しています。非営利型の一般法人なども含まれるため、認定法上の公益法人に比べて範囲が広いです。
非営利型法人には、「非営利性が徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」の2つの類型があります。 「非営利性が徹底された法人」は、非営利徹底型です。事業により利益を得ること、その利益の分配を目的としない、運営するための組織が適正である一般法人をいいます。
「共益的活動を目的とする法人共益型」は共益型です。会員の会費により共通する利益を図る法人で、事業を運営する組織が適正である一般法人をいいます。
法人税法上の収益事業とは、「販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの」をいいます(法人税法2十三)。
「販売業、製造業その他の政令で定める事業」は、法人税法施行令第5条第1項において34の事業が定められています。
| 法人税法施行令 | |||
|---|---|---|---|
| 34事業に該当する | 34事業に該当しない | ||
| 認定法 | 公益目的事業 | 仮に34事業に該当する場合であっても、認定法上の公益目的事業は、収益事業の範囲から除かれます | 課税所得の範囲に含まれません |
| 収益事業等 | 法人税法上の収益事業 | 仮に認定法上の収益事業等であっても、法人税法上の収益事業ではありません | |
認定法上の収益事業等と法人税法上の収益事業は、定義がまったく異なります。
認定法上の収益事業等が課税所得の範囲になるとは限らないため、留意が必要です。
一般法人は登記のみで設立でき、公益事業以外の収益事業も自由に行えます。
しかし公益法人になるためには公益認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。設立後も、さまざまな認定基準をクリアする必要があるのです。
公益法人を目指す方は、まずは一般法人を設立し、公益認定を受けられるように組織や事業内容を整備していくとよいでしょう。