社宅制度で費用を経費とするための要件を解説しています。「借り上げ社宅」「社有社宅」の違いや住宅手当との違い、社宅制度を活用する際の企業、従業員それぞれのメリット・デメリット、注意点も紹介しています。社宅制度の導入・利用を検討されている方は参考にしてください。
2023.09.15(最終更新日:2024.02.01)

社宅制度で費用を経費とするための要件を解説しています。「借り上げ社宅」「社有社宅」の違いや住宅手当との違い、社宅制度を活用する際の企業、従業員それぞれのメリット・デメリット、注意点も紹介しています。社宅制度の導入・利用を検討されている方は参考にしてください。
2023.09.15(最終更新日:2024.02.01)

社宅とは、企業が従業員を居住させるために用意した住宅のことで、従業員の住居負担を軽減させるための福利厚生制度の1つです。
従業員は、個人で物件を借りるよりも社宅を利用した方が居住費を抑えることができ、転居が必要な新入社員や、転勤により短期間で物件を探さなければならない従業員にはありがたい制度です。社宅を利用することで、住宅手当を受け取る場合と比較して、所得税や社会保険料などの税負担を軽減できるメリットもあります。
企業にとっては、社宅関連の経費を計上することで税負担の軽減を図ることもできます。
社宅には「借り上げ社宅」と「社有社宅」の2種類があります。
借り上げ社宅とは、企業が法人名義で契約した住居のことです。
あらかじめ企業が物件を選んで契約する場合もありますが、従業員が物件を選び、企業が契約手続きをする場合もあります。
従業員にとっては後者の方が住居選びの自由度が高くなるため喜ばれますが、企業にとっては事前にまとめて手続きが進められないため、契約手続きに手間がかかります。
社有社宅とは、企業が所有する居住用物件を従業員に貸し出す社宅制度です。
自社所有の物件のため場所が決まっており、従業員同士やその家族と交流する機会が多くなります。
社有社宅では企業が物件の維持管理や修繕などの対応を行うのが一般的で、固定資産税も負担する必要があります。

住宅手当とは、従業員の家賃補助を目的として、従業員に現金を支給する福利厚生制度です。
多くの場合、通常の給与に住宅手当を上乗せして支給されます。制度の名称は企業によって異なり、「家賃手当」や「家賃補助」などと呼ばれます。
社宅を利用する場合と住宅手当を受け取る場合の違いを比較するため、給与額200,000円、家賃80,000円、企業がその半額を負担するケースを例に紹介します。
(単位:円)
| 社宅 | 住宅手当 | |||
|---|---|---|---|---|
| 従業員の給与 | 企業の負担 | 従業員の給与 | 企業の負担 | |
| 給料 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 住宅手当 | 40,000 | 40,000 | ||
| (課税支給額) | 200,000 | 200,000 | 240,000 | 240,000 |
| 社会保険料 | 28,300 | 28,300 | 33,960 | 33,960 |
| 源泉所得税 | 3,770 | 4,980 | ||
| 家賃天引き | 40,000 | |||
| 家賃支払い | 40,000 | 80,000 | ||
| 家賃支払い後の手取り | 127,930 | 121,060 | ||
| 企業の負担総額 | 268,300 | 273,960 | ||
(※簡素化するため協会けんぽ(R5)東京、独身。介護保険、雇用保険、住民税なし。また、社会保険料は折半。こども子育て拠出金は省略。)
従業員は社宅を利用する場合、給与から家賃40,000円が天引きされ、手取り金額は127,930円になります。住宅手当の場合、手取りの金額は121,060円となり、6,870円の差額が出ます。
税法上、住宅手当は給与と同等に取り扱われるため、社会保険料・所得税の課税対象に含められ、上乗せされた分だけ税負担が重くなります。社宅の場合には、社会保険料も所得税も課税対象とならないため、その分手取りの金額が多くなるという仕組みです。
また、企業の立場からみても、住宅手当の場合には負担額が5,660円多くなります。これは企業が従業員の社会保険料を半分負担するためです。

社宅制度を導入すると給与課税されないという大きなメリットがありますが、現金で支給される住宅手当や、入居する従業員が直接契約している場合には社宅の貸与として認められず課税対象になります。
従業員に対する社宅と、役員に対する社宅の場合では、給与課税されない要件が異なる点にも注意が必要です。
従業員が社宅を利用する際に給与課税されないための条件としては、以下1〜3の合計額(賃貸料相当額といいます)の50%以上を従業員から徴収することが挙げられます。
借り上げ社宅の場合でも、社有社宅の場合であっても同じ方法で計算します。
この計算をするためには、物件の所有者に依頼して固定資産税の課税通知書などを確認し、課税標準額や建物の総床面積を確認する必要があります。
例えば、賃貸料相当額が月8万円である場合、
出典:国税庁公式サイト「No.2597使用人に社宅や寮などを貸したとき」
役員に社宅を貸す場合には、従業員の場合と賃貸料相当額の算定方法が異なります。
賃貸料相当額の算定方法は、社宅の法定耐用年数と床面積によって「小規模な住宅かどうか」を判断し、以下、該当の計算式で算定します。
小規模な住宅とは、いずれかに該当するものです。
上述の、従業員の計算式と同じ方法で計算します。
社有社宅の場合は、次の合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
借り上げ社宅の場合は、物件の賃料50%の金額と、社有社宅で算出される賃料相当額とのいずれが多い金額が賃貸料相当額になります。
なお、床面積が240㎡を超えるものや、プール付きの物件など、「豪華な社宅」と判断された場合は、通常払うべき家賃が賃料相当額になります。
出典:国税庁公式サイト「No.2600役員に社宅などを貸したとき」
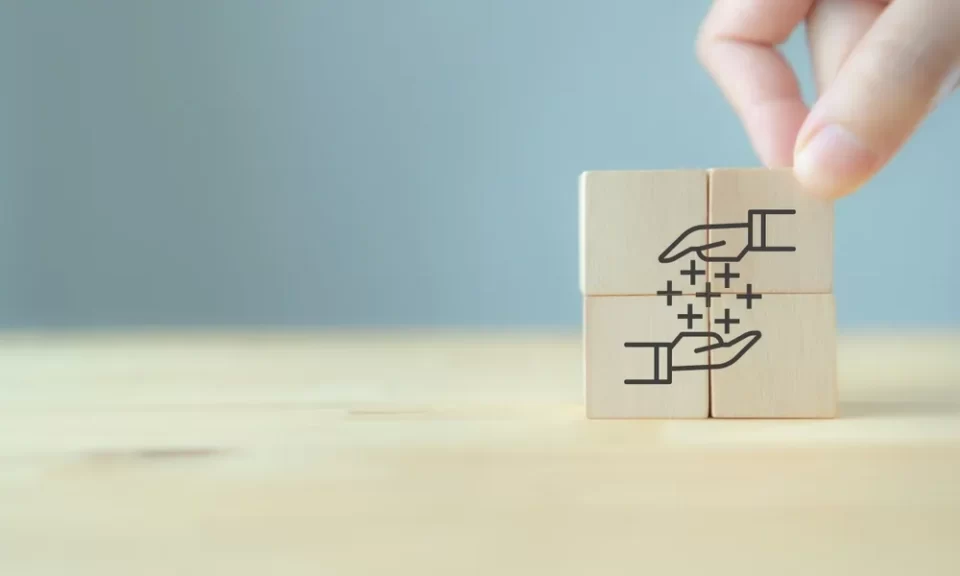
社宅制度は従業員だけでなく、制度を導入した企業にもメリットがあるとされています。
ここでは企業・従業員双方のメリットについて解説します。
社宅制度に限らず、福利厚生は従業員の身体的・精神的な健康維持を目的としています。
福利厚生が充実していると、従業員の仕事に対するモチベーション維持、向上に繋がります。
しかし、従業員側だけにメリットがあるわけではありません。社宅制度を活用することで、企業側にもメリットがあると考えられます。
社宅制度は従業員の家賃負担を軽減できるため、従業員の生活を安定させ、仕事に対するモチベーションにも良い影響を与えるでしょう。
離職防止にもつながり、企業の組織力向上が期待できます。
福利厚生が充実している企業は、採用活動の際に大きなアピールポイントとなります。
企業が負担した社宅に関する費用は、法人税法上、損金に算入できます。損金に計上する額が増えると課税対象となる所得が減るため、法人税の負担が軽減します。
社有社宅の場合には管理費や修繕費、固定資産税など多くの支出を伴いますが、すべて事業に関係する支出のため、法人税法上の損金に計上できます。
家賃は支出の中でも高い割合を占めるため、住宅に関する支援は従業員にとって満足度が高い制度といえます。
社宅制度を従業員が利用するメリットとして、以下の3つが挙げられます。
社宅制度は、生活費の大部分を占める家賃の負担を軽減できるため、従業員にとっては大きなメリットです。
家賃負担が軽減されることで生活資金に余裕が生まれ、貯蓄形成もしやすくなります。
住宅手当の場合は、支給される金額が給与と同じ取り扱いになるため課税対象となります。
社宅の場合は、予め家賃分の金額が給与から天引きされ、その分の所得が減り、結果として税負担が軽減されます。
個人が不動産会社などを通じて賃貸借契約を行う場合、まず入居審査があり、それを経て賃貸契約が成立すると、敷金や礼金、火災保険料などの手続きも発生します。
社宅であれば入居審査はなく、敷金や礼金が発生することもありません。
個人契約の場合に発生する手続きが簡素化されるのも、従業員にとってはメリットといえます。

従業員側、企業側双方にメリットが多い社宅制度ですが、思わぬデメリットもあります。
ここでは、企業側と従業員側のデメリットについて紹介します。
社宅制度では、以下の2つの点から企業側の経済的負担と業務負担は大きくなりやすいとされています。
借り上げ社宅の場合、物件の管理は管理会社や不動産会社が行うので手間はかかりませんが、契約時や契約更新時、解約時など、手続き業務は企業の負担になります。
一方、社有社宅の場合には、管理や修繕、維持の対応が必要です。設備や運営上のトラブルも担当者が対応することになります。土地や建物に対する固定資産税や修繕費など、経済的な負担もかかります。
企業があらかじめ物件を選んで契約している借り上げ社宅の場合、居住する従業員がいない期間は空室になり、空室期間中は賃料全額が企業の負担になります。入居や退去のタイミングによっても、空室が発生する可能性があります。
従業員が入居を希望するタイミングで住宅契約を行うことも視野に、自社に合った契約方法を検討しましょう。
社宅制度は従業員のための福利厚生ですが、一定の制約もあります。
以下の点がデメリットとなることも把握しておきましょう。
社宅の場合、従業員が物件を自由に選べないケースがあります。
借り上げ社宅の場合、企業が物件を選択して契約しているケースと、従業員が物件を選択し、企業が契約手続きを行うケースがありますが、前者の場合は自由度が低くなります。
後者の場合でも、勤務地から「何分以内」「何駅以内」といった制約があり、希望する条件の物件を選べないことも考えられます。社有社宅の場合には、そもそも物件を選択することができません。
社宅は、退職すると当然ながら利用できなくなります。社有社宅はもちろん、借り上げ社宅の場合も退去が必要な可能性が高いです。
従業員が選んだ物件を借り上げ社宅としている場合、場合によっては賃貸人に承諾を得て、個人との契約に変更できることもありますが、この場合は家賃が全額自己負担になる点に注意が必要です。

社宅制度を導入する際、企業はどのようなことに注意すればよいのでしょうか。
導入にあたってのポイントを4つ紹介します。
給与課税を避けるため、従業員から賃料の50%以上を徴収する必要があります。
徴収額を決定する際には、固定資産税の通知書など必要な書類を揃えて算定し、従業員の負担割合に注意しましょう。
役員が社宅を利用する場合は、給与課税されると法人税上の損金算入も認められなくなる点に注意が必要です
社宅制度を運用する際は、社宅に関する規定「社宅規定」を作成しましょう。
社宅規定とは、企業が社宅を管理するうえで基準となるルールです。
社宅の賃貸、使用、管理に関するルールを定めることで、トラブル防止や入居・退去時の手続きをスムーズに行うことができます。
入居できる条件、賃料とその負担割合、その他費用の取り扱い、入居期間、退職時の対応など、可能なかぎり細かく基準を明記するのがポイントです。
社宅制度では、物件を会社名義で契約する必要があります。
従業員名義で契約した物件についての補助は住宅手当に該当し、給与課税の対象となります。
社宅に関する費用のうち、共益費は家賃と同様に社宅家賃に含められますが、水道光熱費と駐車場については含められません。
水道光熱費は、原則、個人が負担すべきものとされ、企業が負担した場合には給与課税されます。ただし、以下2点を満たす場合は、給与課税されないとされています。
駐車場についても、駐車場は「家屋」ではないため、原則社宅家賃に含まれません。
したがって、駐車場の利用料を企業負担にすると給与課税されます。

「社宅」は福利厚生の1つで、従業員の住居負担を軽減させる制度です。従業員は生活費を抑えられるだけでなく、住宅手当の支給を受ける場合よりも所得税や社会保険料などの税負担を軽減できるメリットがあります。
企業にとっては、従業員の満足度を向上させつつ、社宅関連の経費を計上することで税負担の軽減を図ることができます。社有社宅、借り上げ社宅の2つの選択肢があるため、どちらが自社の実態に合うか検討が必要です。
メリットとデメリットを踏まえ、適切な条件を設定しながら社宅制度の導入を検討しましょう。