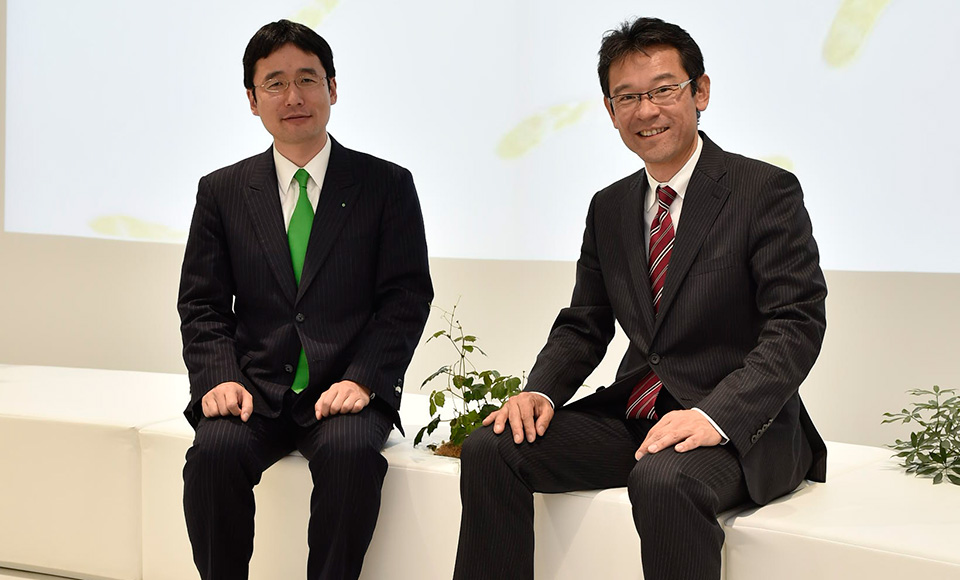目次
- 種を蒔き、育て上げる。
農学こそ、ベンチャー。 - ミドリムシとの出合いを機に、
循環型社会の実現を目指す。 - 多様な可能性を活かし、
常に新しい挑戦を。 - ユーグレナとの出会いから参画まで。
- IPOを目指すということ。
- ユーグレナとして、そして個人として抱くビジョン。
- 求められるハードルは高いが、それを実現していく。
- CFOに求められる資質とは。
- 後輩CFOへのメッセージ。
種を蒔き、育て上げる。
農学こそ、ベンチャー。

廣渡ユーグレナさんとは、2008年からのおつきあいになりますね。
出雲私どもは、2012年に大学発のベンチャー企業として日本で初めて東証マザーズに上場を果たしました。そのずっと以前から、AGSさんにはいろいろとご支援をいただいています。
廣渡初期からお手伝いをさせていただき、一部上場後も継続したおつきあいができていることを何より光栄に思います。今日は、出雲社長が起業に至った動機や、上場までのお話、また御社の現在の事業や未来の展望などをうかがえればと思っています。
ところで、“ベンチャー”という言葉は今となっては普通に使われますが、15年ほど前まではまだ母数も少なかったですよね。お仲間と起業されたのが2005年ということですが、出雲さんは、ベンチャーとはどんな存在と捉えていますか?
出雲私自身、理系の出身ですが、ベンチャーに携わって思うのは、これはまさに農学そのものだということです。なぜって、農業は種を土に蒔くことから始まり、台風や日照りを乗り越えながら、作物を育て上げ、実ったものを収穫しますよね。それを実際に食べておいしいか確かめ、翌年はもっとおいしく育てようと知恵をしぼり、再び種を蒔いて育てる。それをひたすら繰り返します。まさに農学自体がベンチャー(冒険的)だと思いませんか?
廣渡試行錯誤しながらより良いものを作るために、時には品種改良も重ねる。
出雲でも、頭の中でどんなに計算しても答えは出ない。まずは実践。やってみないとわからない。
廣渡まさに! それっていい話ですねえ。
出雲ありがとうございます。そうなんです、だから実践主義の農学の人がベンチャーをやればうまくいくと思うし、ぜひやって欲しいと思っています。
廣渡ところで、出雲さんが起業に至ったきっかけか知りたいですね。少年時代から目指しているものがあったのですか?
出雲公務員か会社員です(笑)。私は、多摩ニュータウンで育ちました。そこで暮らす世帯は、うちを含め、父親は企業に勤めているか公務員ばかりで、自営業の方はひとりもいらっしゃらなかった。自分のようになりなさいという教育は受けたことはありませんでしたが、そんな環境ですから、ただ他を知らなかった。個人で事業を立ち上げるなんて、ましてやベンチャーでやっていこうなどと考えもつかなかったです。
ミドリムシとの出合いを機に、
循環型社会の実現を目指す。

廣渡その考えが変わったのは、やはり、ミドリムシに携わるようになってからですか?
出雲はい。大学1年、18歳の時に学外活動でバングラデシュに行った時、そこで子供たちの貧困と栄養事情の悪さに直面し、衝撃を受けました。世界の食料問題を解決したいという思いを抱いていた中で、ミドリムシを知りました。
廣渡やはり会社よりもミドリムシが先だったんですね。
出雲ミドリムシは藻の一種ですが、その中に、人間が生活するために必要な59種類の栄養素を含んでいるんですよ。植物は動けませんよね。動物は光合成ができない。ところがミドリムシは両方できる。つまり植物と動物の力を兼ね備えているわけです。これを培養、加工して子供達に飲んでもらえたら、元気にしてあげられる。非常にシンプルな考えがきっかけです。
廣渡そこからなぜ起業に至ったのですか?
出雲思い立ったのは大学3年の頃です。ミドリムシがいかに優れた栄養を含み、人に有用かという研究は1980年代から続けられて来ました。でも、これを大量に培養する技術は研究されて来なかった。量産すれば社会の役に立つのは明らかですが、それは大学の研究の方向性と違う。だったら、培養と活用のために自分が会社を作らなくては、と意識が変わっていきました。
廣渡そうだったんですね。そこから実際の起業を経てその後の苦労や紆余曲折は、方々から尋ねられる機会も多いのではないですか? みなさん興味がおありでしょう。
出雲そうですね。苦労話も、もちろん聞かれればお答えします。でも、これまでのことをよくご存知の廣渡さんだから本音を申し上げますけど、はたから見たらきっと大変だと思われることも、自分自身では大変と思ったことがないんです。ミドリムシ(の培養と活用)は、誰かにやれと言われてやっているわけではなく、好きでやっているんですから。
廣渡なるほど。素晴らしいです。
出雲ユーグレナを2005年に設立して、ミドリムシの培養に成功したのがその年の年末でした。さっそく翌年の頭から営業を始めるのですが、そこでまず100社回ろうと。ミドリムシと聞いて、それが高性能の藻と最初から分かる人はまずいません。でも、根気よく説明をすれば、たとえ100社のうち99社断られても、1社は買ってくれるだろうという予測を立てました。
それから1日平均3社、2年間で約500社営業しましたが、買ってくれる会社は結局0でした。当然売上も2年間0円。それでもなお、私はピンチとは思っていませんでした。
廣渡まさに、好きでやっているからこそですね。
出雲ベンチャーは天候諸々に左右されて当たり前。でも、そんな時にターニングポイントとなる出会いがありました。ミドリムシの話を熱心に聞いていただける方が、ついに現れたんです。半年のデューデリジェンスを経て、ミドリムシの可能性に出資し、販売を担当していただけることになりました。伊藤忠商事さんです。このことがきっかけとなって、誰もが知っている名だたる企業から次々とお声をかけていただくようになりました。
多様な可能性を活かし、
常に新しい挑戦を。

廣渡食品から始まったけれど、今、様々な事業へ展開していますね。ユーグレナさんが「5F」として掲げるFood(食品)、Fiber(繊維)、Feed(飼料)、Fertilizer(肥料)、Fuel(燃料)という多段階利用の仕組みが固まったのはいつですか?
出雲2009年です。最初からやりたかったのは、FoodとFeedで、当初は食べることばかり考えていました。でも、いろいろな企業さんと出会わせていただくたびに、共同研究を通して、ミドリムシにはこんな使い道や可能性もあるんだ! と気づかせていただいています。
廣渡お話をお聞きしていると、全くお客さんの取れなかった2年間も、名だたる組織と協働している今も、出雲さんが注いでいる力に違いはないですよね。ただ、上場を果たしたことで、より多くの企業とインパクトのある事業に携われたり、事業が形になるスピードが増すという点では、やはり上場することの意義、ダイナミックさを感じませんか。
出雲もちろん感じます。例えばバイオ燃料研究などは数年で完結するような話ではなく、数十年単位の長期的な事業です。完結するその時まで私たちが存続できるということを示すためにも、四半期ごとに財務諸表を開示して、一部上場しているという事実は、大きな意味を持っているんです。じつは、私たちが東証一部上場を果たした際にそれを一番喜んでくれたのは、ミドリムシの可能性を信じて協働の名乗りを上げてくれた企業さんと、古巣である東京大学のアントレプレナープラザ(東京大学産学協創研究推進本部)でした。
廣渡出雲さんたちのおかげで、アントレプレナープラザという場を作った甲斐があったと嬉しかったはずです。ベンチャーの世界で、頑張ったなりに結果を出せる人が育ち、努力をした企業が社会にくさびを打てるようになってきている。もちろん、必ずしも理論だけでは成功できない世界ですが。
出雲そこが農業と一緒です。失敗しながら試し続ける。
廣渡そういう意味でもユーグレナさんは若手の希望の星です。最後に、これからIPOを目指す企業家へメッセージをお願いします。
出雲ベンチャーは農業です。育ちが悪くなったらAGS!(笑)
冗談ではないですよ。「専門外で無理をしてはいけません。AGSさんは、私たちの事業にまだ誰も目をつけていない時代から支え、一ミドリムシが一部上場ミドリムシになるまで、フルサービスでサポートをしてくださいましたから。AGSの肥料サービスで、みなさんの花が立派に開くことを願っています。

株式会社ユーグレナ 取締役 CFO
永田 暁彦氏 インタビュー
ユーグレナとの出会いから参画まで。
ユーグレナとの出会いは2007年です。当時は投資会社に属していたのですが、その会社で担当したのがきっかけです。当時のユーグレナは、まだ他の会社に間借りをしていて、社員数も少ない、小さなベンチャーでした。ただ、社長の出雲を含め経営陣が自分と同じ年代だったということや、もともと環境問題に関心が強かったこともあり、個人的に社の取り組みに意義と将来性を感じていました。
2008年、投資会社の意向で派遣役員になりました。当時は資金調達を含めた財務面を担う人材が他におらず、欠けている部分にたまたま自分が持っているスペシャリティが重なったことが大きかったと思います。出雲から正式にユーグレナへ来て欲しいとの打診があったのは翌2009年6月。その場では「少し待ってください」とお返事しました。社内で役員として認めてもらうため、エクイティファイナンスを達成し、実績を作ってから入社したいという気持ちが強かったからです。数社との資本提携と資金調達を完了させた2010年4月、正式に役員として参画しました。
IPOを目指すということ。
上場への準備は、2009年からスタートしていました。
ユーグレナは食品事業からスタートしましたが、すでにバイオ燃料開発を視野に入れており、それには当然、莫大な研究開発費が必要になるわけです。マザーズはベンチャーを支援するマーケットなので、基本的には赤字上場を認めてはいます。ただ、研究を続ける意義を汲み取って上場できる相手、証券会社がいるかどうかが、最初のテーマでした。上場するために研究を諦めるという選択肢もあったのかも知れませんが、ジェット燃料の分野は世界競争ですから、フルスピードで開発を進めたい。結局、上場基準を満たすためにも研究開発費以上にミドリムシを売ることが求められました。そこは、役員でマーケティング部の福本が頑張ったところですね。
企業価値を測る時にPER(株価収益率)という指標がありますが、我々の本質的な価値は研究開発にあります。研究開発すればするほど利益は減り、PERが下がるわけです。でも、そこで言いたいのは「我々は食品会社ではなく、バイオテクノロジーカンパニーである」ということ。すでに価値化されている食品を売って収益を得ながら、未来に価値あるものの研究開発も行っている。そうした企業価値を、総合的に評価してほしいというのが僕たちの気持ちでした。つまり、IPOに際して、このことをきちんと理解してくれる証券会社としかお付き合いはできないという結論に至ったわけです。我々がどういう会社であり、どんなことを目指しているか。そういう定性的な評価を世の中に伝えていくことが、我々が上場するに際して最も重要なファクターでした。これが、他の企業さんとユーグレナが最も異なる部分ではないかと思います。
ユーグレナとして、そして個人として抱くビジョン。
ユーグレナのミッションは、「人と地球を健康にすること」です。そのためには、あらゆる可能性を考え、実行したい。バイオ燃料にしても、研究開発だけで終わるのではなく、さまざまな組織と連携し、その技術が実際に活用されるまで、社会が変革するところまで責任を持ちたい。会社の経営戦略を管掌する者として、そこに責任を持ちたいと思っています。自分たちが力点となり、本気で地球と人を健康にするための組織づくりと資金調達、そして社会的認知を強めていかなければいけません。
ユーグレナは特殊な会社です。大学発のベンチャーで黒字を出し、一部上場も達成しました。大学発のベンチャーで頑張っているところは今までもありました。でも、なかなか成功しなかったのはなぜか。それは今まで“轍”がなかったんですよね。起業をしてから、どこをどうやって歩いて行けばいいかわからなかった。今、いろいろなベンチャーの方たちに問われれば、「僕らはこうやったよ!」と、実体験からアドバイスができるし、その根底には、けもの道すら無かったところを僕らは開拓してきたという自負があります。僕たちの後を、みんながどんどん歩けるようにして、やがて最後は舗装された道路にしたい。僕はもともと投資側にいた人間なので、将来を語ってお金を受け取ることの重みは理解しているつもりです。機関投資家、個人投資家に関わらず、未来や夢を語って、期待以上の成果を社会に還元したいという気持ちがある。だからこそ、テクノロジーを持った人たちが社会で起業し収益化するための支援をしたい。そういう意味で、ユーグレナインベスメントの立ち上げは、個人のビジョンとも重なります。
求められるハードルは高いが、それを実現していく。

求められる仕事の要求水準は、とても高いです。例えば、僕らは今、アメリカのシェブロン社と組んで、日本初のバイオ燃料培養施設を作ることを進めているのですが。ある時、一度もアメリカから出たことが無いテクノロジーのライセンスを、もらってこいというお達しだけが届く。僕たちはその会社の誰一人にも会ったことが無いのにです(笑)。それは言うなれば、北海道に1秒で行きたいということと同じ。僕は、自分がドラえもんだと思う時があります。ただし便利な道具が出てくるポケットは持っていない。だから実現のために懸命に考えるんです。そう、私にとってのポケットは仲間かもしれませんね。でも、こういう仕事はそもそも出雲の発想が無ければ誰もやろうと思わない。ですから、想像もできないような価値を見つけて僕たちに高めの球を投げ続けるのが、社長のミッションなのだと理解しています。発想する人がいないと事業は生まれないし、僕たちがいないと実現できない。そこは補完関係なのだと思います。
CFOに求められる資質とは。
個人的には、CFOは単なるファンクションだと思っています。ベンチャーのCFOといえば、お金を調達するのが重要な機能だと思われがちですが、それは一番下層にある機能でしかない。優れたファイナンスのストラクチャーを考えられる人が、必ずしも資金調達できるわけではない。ある意味過激な言い方かもしれませんが、僕は、一番優秀な詐欺師こそがお金を調達できると思っているんです。なぜなら、利益がなくても、この会社には数十億の価値があると言ってお金を集める。でも、実現したら詐欺ではなくなるわけです。長いスパンで見た時、資金調達は入り口でしかない。約束したことをどのように果たし、語った未来をどのように実現するか。僕はそれが何より大事だと考えます。その際CFOの役割として一番重要なことは、社内外、特に社内のインベストメントだと思います。どのプロジェクトにどう投資するか。その見極めが非常に重要です。そういう意味で僕は自分をCFOとは思っていないんです。投資するのが仕事であれば、管理会計で実態を理解するのも、理解したものを評価するも仕事だし、実現しようとすると、働いている人を最適化するために人事は手放せないし、事業開発もM&Aも・・・あらゆることをやらないと実現化されないと思っています。経営企画とファイナンスはセットであるべきだし、アカウンティングと管理会計を同じ人間が担当することも大切だと感じています。お金を投資するのと同様に人をどう配置するかも重要。こうしたファンクションを全て抱えているのはそういう理由です。求められるのは「投資する能力」だと思っています。
後輩CFOへのメッセージ。
大切なのは、自分が、会社の目標を達成するためのファンクションであることを認識することではないでしょうか。あえてCFOという世界観で立場を作らずに、会社の機能として、目的を果たすためには何をする必要があるか。それを、ファイナンスと言う領域の責任を持って取り組むということが大切なんだと思います。

出雲 充氏
株式会社ユーグレナ
代表取締役社長人と地球を健康にするーー。
農学で培った実践の精神で、
社会を変革させていきたい。2002年、東京大学農学部卒業。東京三菱銀行(現三菱東京UFJ銀行)を経て、2005年、取締役3名でユーグレナを立ち上げ、代表取締役社長に就任。同年末、社の研究機関にて、世界で初めて微細藻類ユーグレナ(和名・ミドリムシ)の食用屋外大量培養に成功。現在は食品開発を根幹に、バイオ燃料研究にも力を注ぐ。

永田 暁彦氏
約束したことを実現する、
語った未来をどう実現するか。
それが何より大事だと考えます。株式会社ユーグレナ 取締役CFO
株式会社ユーグレナインベスメント 代表取締役社長慶応義塾大学商学部卒。独立系プライベートエクイティファンドを経て、2008年にユーグレナの取締役に就任。資金調達や資本提携、M&Aなどファイナンス部門および、広報・IR、人事、事業戦略、管理部門構築など、幅広い領域を担っている

株式会社ユーグレナ
設立:2005年8月
事業概要:ユーグレナ等の微細藻類の研究開発、生産・ユーグレナ等の微細藻類の食品、化粧品の製造、販売・ユーグレナ等の微細藻類のバイオ燃料技術開発、環境関連技術開発・バイオテクノロジー関連ビジネスの事業開発、投資等
所在地:東京都港区芝5-33-1 森永プラザビル22F
廣渡 嘉秀
Yoshihide Hirowatari
株式会社AGSコンサルティング
代表取締役社長社会に貢献するべく努力を重ねる企業を、
陰ながら応援することは、喜びでもある1967年、福岡県生まれ。90年に早稲田大学商学部を卒業後、センチュリー監査法人(現 新日本監査法人)入所。国際部(ピートマーウィック)に所属し、主に上場会社や外資系企業の監査業務に携わる。94年、公認会計士登録するとともにAGSコンサルティングに入社。2004年に代表取締役専務、06年に副社長を経て08年より社長就任。09年のAGS税理士法人設立に伴い同法人代表社員も兼務し、現在に至る。